|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.3.31 最終確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードディスクにも光学ドライブにも対応しているACARD社製 AEC-7720U/UW ACARD社のSCSIDEブリッジ製品は、カタログ上では電気特性的に「ATAPI専用」と「ハードディスク専用」が明確に区別されています。 同社のAEC-7722は、光学ドライブ専用のATAPI規格製品ですが、AEC-7720UとAEC-7720UWだけは、設計が古いことが幸いなのか、ATAPI(CD、MO、ZIP)機器でもハードディスク(IDE)でも使えます。 ACARD製品に関する本サイトの記載事項につきましては、SE/30においてのみ確認した内容ですので、ほかのMac製品、Windows製品には該当しない可能性があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC-7720UW ACARD社現行モデルのIDE対応製品のなかでは最古参のモデルです。 AEC-7720UWはUltraWide規格で、Ultra SCSI規格のAEC-7720Uに比べて転送速度が2倍、デージーチェーンも15台まで可能です。 某国のDVDの大量複製目的で使われていたためか、中古市場ではUWのほうがたまに見つかるようです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACARD製 AEC-7720UW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「SCSIDEブリッジ」は「SCSI to IDE Bridge」の略で、IDE(ATA,ATAPI)およびSATAデバイスを、SCSI(標準SCSIからUltra320まで)に変換するACARD社の製品群です。 同社の当時のモデルの中でMacに関連するSCSI仕様の製品は以下の3種類です。 ドライバーソフトも、SCSI-ID以外の特段の設定の必要もなく、簡単に使えます。 実際の最大転送速度はSCSIコントローラに依存するため、OldMacでは5MB/Sまたは10MB/S以下となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC-7720UはSE/30の内蔵SCSIポートの50ピンフラットケーブルがそのまま使えますが、7720UWのほうは68Pin仕様のため50-68ピン変換アダプタが必要です。 当店では、本装置を使ってPowerbookG3で使っていたIDEの内蔵2GBが、以下のように「SCSIの固定ハードディスク」として認識されることを確認しました。 接続方法は、IDE2.5"内蔵2GB(44ピン)を2.5"-3.5"変換で40ピン変換してAEC-7720UWのIDE側につなぎ、SCSI側の68ピンを50-68ピン変換で50ピンに落としてからSE/30の内部SCSIポートに接続です。外付けHDD内の漢字Talkで起動して2GBドライブがマウントされました。 |
||
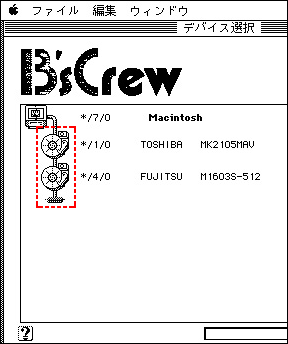 |
||||||||||
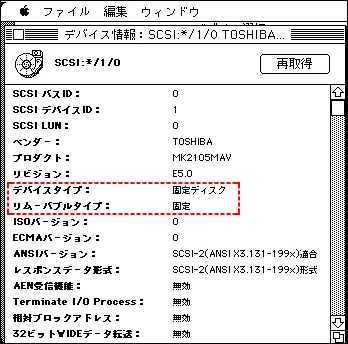 |
||||||||||
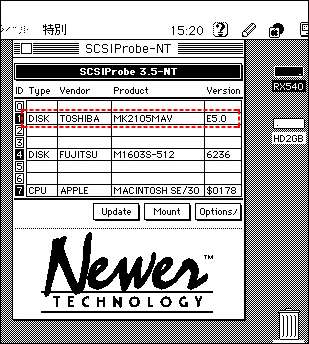 |
||||||||||
SCSI Probe-NTでハードディスクとして認識 |
フォーマッタソフトでも起動HDDと同じアイコンの表示 |
同ソフトで詳細情報表示。固定ディスクとして認識 |
||||
2014年の「Macintosh Floppy Emu」の登場により、SCSIポートを使わないHDD環境ができたことはよろこばしいことですが、これがいつまでも市場供給されるとは限りません。可能な限りのSCSIへの代替手段を調べておきましょう。 IDEをSCSIに変換するデバイス(ACARD社SCSIDEブリッジや中古SCSI-HDD内の変換基板)が当面は入手でき、産業用制御機器内に使われているIDE互換のDOM(Disk On Module)もしばらくは生産が続くことから、やろうと思えば、新品ACARD社SCSIDEブリッジ+ 新品DOM といった「新品のSCSI環境」も可能です。 本ページでは外付けSCSIケース(IDE変換タイプ)を利用して、ちゃんとしたSSD化の方向性をめざします。
筆者は、CF-SCSI変換やSD-SCSI変換基板などのメディア変換基板の商品については、コントローラの部分でちゃんとウェアレベリング(Wear leveling)をしているのか、各製品の紹介部分において記述がないので信用しておりません。 CF、SD自体はウェアレベリングがない基本的なNANDフラッシュメモリ機能だけですから、書き込みの平均化はコントローラの仕事です。よってACARD社SCSIDEブリッジを使う手法もふくめて、すべて「擬似的にSSDらしく見せているだけ」と判断しております。 別の言い方をすれば「ウェアレベリングのないものはSSDの名に値せずその価値がない」です。DOM(Disk On Module)はSSDのひとつですので、データの保持期間や書き換え寿命などNANDフラッシュ製品固有の性質がありますが、コンパクトでHDDマウンタなども考える必要がなく取り扱いが簡単です。入手についてはこちらを参照。 |
||
 |
 |
 |
||||
KingSpec製 4GBB KDM-40VS.004GSS |
PQI製128MB DJ0128M22RF0 |
DJ0128M22RF0 の裏側の5V電源端子 コネクタは1.5mmピッチJST製ZHシリーズ (KingSpec用は2.0mmピッチJST製PHRシリーズ) |
||||
結果は、変換基板、フォーマッタ、DOMの相性しだい このテストでは、IDEハードディスク搭載タイプの外付けSCSIハードディスク装置からHDDをはずしてかわりにDOMを装着します。 当然、内部のIDE-SCSI変換部分は、100%完全にSCSI動作するわけではありませんし、フォーマッタソフトのほうも本来がSCSI規格用に作られていますがSCSI規格自体も改訂をくり返していますので、本テストで使用したバージョンがどのSCSI規格に対応しているのかよくわかりません。またDOMのほうも固定ディスクモード(True IDE)とはいいながら、あくまでもNANDフラッシュ製品でありIDEハードディスクとは別物ですから、本テストの結果については、変換基板、フォーマッタ、DOMの相性による部分が多分に反映されているとお考えください。
なお各外付けHDDの仕様上のOS対応は DSC-U8.4GTR 漢字Talk7.5以降 DSC-U30GTV/USP 漢字Talk7.5.3以降 LHD-E40SU 漢字Talk7.5.3以降 となっています。 |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||
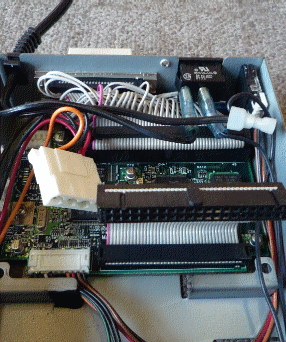 |
||||||
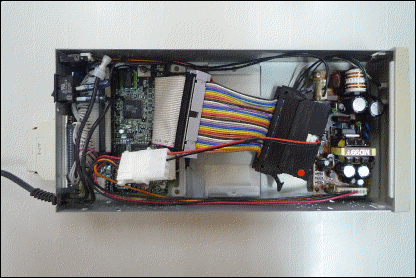 |
||||||
Buffalo製 DSC-U30GTV/USPのIDEハードディスクをはずして代わりにDOMを装着 |
||||||
通常のIDE3.5"HDDの40ピン・メスと4ピン電源コネクタ 40ピン基板側は基板直付け(Logitec製も同じ) 後方の基板SCSI 50"ピンコネクタは着脱可(Logitec製は2段ハーフ50ピンコネクタが基板に直付け) |
DOM装着専用の両端がIDE3.5"HDDの40ピン・ヘッダーコネクタの自作ケーブル(高価なイジェクトレバーつきでなくてもDOMは簡単に着脱可能) 中継用IDC(圧接)リボンケーブル用ヘッダー 上:ヒロセ電機 HIF3BA-40PD-2.54R-MC 下:Wurth Elektronik社 61204025821 (RSオンライン品番823-6654) |
|||||
Copyright © 2012-2025 Namio Nakajima www.marushin-web.com |
||||
